
べらぼう第26話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~
願わくば花の下にて春死なん
松前道廣(演:えなりかずき)と弟の廣年(演:ひょうろく)が島津重豪(演:田中幸太朗)を引き連れ、一橋治済(演:生田斗真)に泣きつく。蝦夷地、ガチで奪われそうになってて草。
でも治済、田沼意次(演:渡辺謙)の上知計画を知って、顔に出すレベルでご立腹。おいおい、そんな露骨で大丈夫!?
一方、田沼意知(演:宮沢氷魚)は吉原で誰袖(演:福原遥)とラブラブタイム。
「春にはそなたと桜の下で…」って、もうプロポーズ級のセリフ、胸キュン止まらん。
だけど現実は非情。米価、下がらん!!
「米穀売買勝手次第」は見事に失敗し、商人たちが爆買い→転売ヤー化→米騰がりっぱなし。徳川治貞(演:高橋英樹)、またも意次に雷落とす。
町では「田沼親子=悪の組織」説が爆誕、意知の吉原通いも燃料投下。
しかも、飢えた流民があふれかえり、江戸マジで詰んでる。
そこに現れたのが、佐野政言(演:矢本悠馬)の父・政豊(演:吉見一豊)。
なんと「系図返せ」と凸ってくるけど、意次がすでに池ポチャ済。詰みすぎて泣ける……。
でも意知、政言をちゃんと引き立てようと頑張る!将軍の狩りに同行させるも、まさかの「雁、いない問題」発生!雁、どこ行った!?
実は、丈右衛門だった男(演:矢野聖人)の意知が隠したという密告が……。でも政言、「あの方(意知)がそんなことするはずない!」って、マジで義の人。泣ける。
蔦屋重三郎(演:横浜流星)はというと、『歳旦狂歌集』の売上が散々で、景気にも絶望モード。
でも、てい(演:橋本愛)が炸裂の一言。
「一挙五得となさるがよろしいかと」この提案が天才すぎて草!
①誰袖を救って、②田沼家の名誉回復、③景気回復、④流民救済、⑤蔦重の夢叶う、ってもう全部のせ企画かよ!
そして動き出す蔦重。
「公儀が米を仕入れて、そのまま売ればいいんじゃね?」という庶民ファーストな神策を田沼屋敷に直談判。
最初は鼻で笑う意知だけど、「これは商いじゃなく政だ」と熱弁する蔦重。
また、誰袖(演:福原 遥)の身請けを心配する蔦重に、意知「誰袖には、もう手は打ったぞ」
!?!?!?!?!?
そう、意知はすでに誰袖に手紙を送ってたのです。
身請けのため、土山の名で動いてくれていた……って、これは尊死案件!
誰袖の涙、蔦重の祝福、エモすぎて全員幸せになれって叫びたくなるやつ。
が、その裏で。
田沼家に贈ったはずの「佐野家の桜」が、なぜか「田沼の桜」として神社で大人気!
政言、何もかも報われない状況に、ついに父の刀を手に取る。
錆びた刀を研ぎながら怒りに震える姿、もう…これはアカンやつや…。
そして、武家装束に身を包んだ誰袖が、大文字屋を旅立つ日。蔦重が贈ったのは、出会いの絵。「幸せになれよ、2人で」
誰袖「言われずとも♪誰よりも幸せな2人に」
あまりに美しすぎる門出……!
しかしその頃、江戸城ではついに——
佐野政言、父の刀を携えて田沼意知に斬りかかっていた!!
幸せの花が咲いたその夜、血の花が江戸に咲くのか——
果たして、田沼意知の運命は……!?
時代を超えて江戸を伝える語り部
時代屋こはる
江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。
べらぼう[用語解説]
一橋治済(ひとつばし・はるさだ)
徳川御三卿のひとつ「一橋家」の当主。将軍・家治の弟で、将軍家に次ぐ超重要ポジション。老中・田沼意次の「蝦夷地(北海道)を幕府直轄にする計画」に不快感を示すなど、政界の黒幕感たっぷり。何を考えているのか読めない、“静かに圧のある男”です。
松前道廣(まつまえ・みちひろ)と弟・廣年(ひろとし)
蝦夷地(北海道)の一部を治める大名・松前家の兄弟。幕府が蝦夷地を取り上げようとしていることに猛反発し、治済に取り消しを懇願します。松前家にとって蝦夷地は「家の命綱」。兄弟そろって切実すぎるお願いに奔走中です。
上知計画
「上知」とは、“土地を幕府に返上させる”こと。つまり大名や旗本の領地を、幕府が取り上げる政策のことです。
ドラマ『べらぼう』で田沼意次が目論む「上知計画」は、蝦夷地(今の北海道)を島津藩や松前藩から召し上げ、幕府の直轄地とする大胆な案。背景には、ロシアの南下政策や北方防衛への危機感がありました。
幕府が直接支配することで、開発を進め、貿易や防衛の拠点にしようとする意次のビジョンは先見の明ありすぎて草ですが、既得権を守りたい大名たちからは猛反発!
意次の政治改革がついに“領地”にまで及びはじめたことで、田沼政治 vs 守旧派の対立はさらに激化していきます。
系図(けいず)の重要性
武士の「家柄」や「血筋」が記された家の履歴書。これがないと、出世どころか武士としての立場すら危うくなることも。佐野政言の父・政豊は、この“家の命”とも言える系図を田沼意次に握られ、苦しんでいます。今なら履歴書を燃やされたようなもの…切なすぎる。
佐野政言(さの・まさこと)と父・政豊(まさとよ)
下級武士の父子。父・政豊は「家の名に恥じるな」と息子に厳しく、息子・政言はそんな父に報いたいと必死。でも空回りばかりで、涙なくして見られない“親子のすれ違いドラマ”。一発逆転のチャンスを得た政言は、果たして父に認められるのか…?
佐野家の桜と田沼の桜
佐野家の庭にあった由緒ある桜。実はこれ、かつて政言が田沼家に献上したもの。それが神社に移され“田沼の桜”として大人気に! 自分の桜がよそで絶賛されてると知った政言は…そりゃあもう、複雑です。花は咲いても、心は晴れない…切ない名場面の象徴です。
誰袖(たがそで)を身請けした「土山」とは?
誰袖を身請け(=遊女を買い取って自由にすること)したのは、実在の人物・土山宗次郎。田沼意知の家臣であり、信頼厚い側近です。
ドラマでは、意知が「自分の立場では直接身請けできぬ」として、土山の名前を借りて誰袖を自由にしようとする――つまり、“名義上の身請け人”が土山という設定。
意知が誰袖に宛てた手紙では「表向きは土山の妾ということになるが、それでもよいなら…」と、控えめながらも愛と覚悟に満ちた言葉が綴られています。
身分と世間の目に翻弄されながらも、心はまっすぐに一人の花魁を想う。
「土山」という名前は、そんな二人の秘めた絆の証でもあるのです。
![[べらぼう第26話あらすじ]<br>江戸の米、爆上がり!蔦重、てい、歌磨の三角関係に泣けた!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/berabo-26-300x200.jpg)
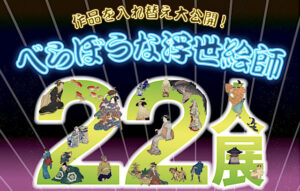
![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)
![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)