
Contents
べらぼう第35話あらすじ~蔦重栄華乃夢噺~
間違凧文武二道(まちがいだこぶんぶにどう)
年が明けた江戸。
松平定信(演:井上祐貴)は朋誠堂喜三二著:黄表紙『文武二道万石通』を手にニヤリ。内容は、源頼朝に命じられた畠山重忠が武士たちを「文に長けた者」「武に長けた者」「ぬらくら(怠け者)」に仕分けるというお話。
そして、絵に自分の家紋“梅鉢”が入ってるのを見つけて大興奮!
「蔦重大明神がそれがしを励ましてくれておる!」いやいや、定信さん、たぶんそれ皮肉です。
ところが本人は本気モードで改革一直線!朱子学者・柴野栗山(演:嶋田久作)をブレーンに迎え、将軍・徳川家斉(演:城桧吏)に紹介。栗山が隣の一橋治済(演:生田斗真)から邪悪なオーラを感じてるあたり、政治バトルの火種がプンプン。
『文武二道万石通』はまさかの大ヒット!でもその解釈がズレてる!
皮肉が伝わらず、「田沼派=ぬらくら」と信じる読者が続出。おまけに歌麿(演:染谷将太)の絵本『画本虫撰』まで「倹約令にぴったり♪」と金持ちたちにバカ売れ。もう風刺どころか、定信の宣伝になってる始末。
定信は「将軍補佐」に就任し、江戸のヒーロー扱い。
一方の蔦屋重三郎(演:横浜流星)は頭を抱える。「いや、これ全部、逆効果やん…!」
その頃、雨の吉原裏。
ひとり寂しそうに帰る歌麿が出会ったのは、耳の不自由な女性きよ(演:藤間爽子)。
かつて自分の“黒く塗りつぶした絵”を拾ってくれたあの人だった。勘違いから始まる優しい再会。言葉が通じなくても、絵で心を伝える歌麿の姿に「尊すぎて泣いた」視聴者多数。
「俺のこと、覚えてます?」きよは首を横に振るが、絵を見て微笑む。
その瞬間、雨上がりの光がふたりを包み込む。—まるで江戸の空が、祝福しているように。
一方、蔦屋は出版仲間たちと“作戦会議”。
恋川春町(演:岡山天音)は「俺の本だけ売れてねぇ」とスネスネモード。
しかし、そこへ大田南畝(演:桐谷健太)が飛び込んでくる——「田沼様が…お亡くなりに…」
田沼意次(演:渡辺謙)、享年七十。かつての恩人が蟄居のまま息を引き取った報せに、蔦重の目に涙がにじむ。
が、定信は冷酷に「葬列への投石を許せ」と命じる。え?投石?それって…やりすぎでしょ!?
曇天に雷鳴が轟き、鳥山石燕(演:片岡鶴太郎)の庭に、源内と同じ羽織を着た“謎の男”が現れる——不思議と霊気漂う場面に背筋がゾクッ。
そんな中、将軍・家斉の“スキャンダル”が発覚。
「大奥の女中と子ども作ったんスか!?」
定信が怒るも、家斉はドヤ顔で「余は子作りに秀でておるし」と開き直る始末。もはや江戸の政治、倫理観ゆるゆるで草。
定信は“心得”の書『鸚鵡言(おうむのことば)』を作り、「政は凧を上げるに似たり」と説く。
が、世間の武士たちはまさかの誤読。「おー!凧を上げれば国が治まるってことか!」…いや、そうじゃない!
これを聞いた蔦重、ピカーンと閃く。「それ、パロディにしよう!」
春町が書いたのが『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』!
黄表紙好きの定信が読んで喜ぶ皮肉な展開に、出版界は再びザワつく。
一方の歌麿は、ついにきよとの結婚を決意。
「俺、ちゃんとしてぇんだ。名を上げて、金稼いで、きよを幸せにすんだ」
まっすぐな告白に蔦重も感涙。
耳の聞こえないきよに早口でお礼をまくしたてる蔦重の姿がもう、愛おしすぎて草。
1789年・寛政元年。空高く上がった凧の糸がふと切れ、ひらりと舞う——
それはまるで、理想と現実の間で揺れる江戸の象徴。果たして、蔦重たちの“書で抗う戦い”はどこへ向かうのか?
時代を超えて江戸を伝える語り部
時代屋こはる
江戸の粋と人情に恋した「時代屋こはる」。ドラマの情景を鮮やかに描き、笑いと涙を織り交ぜながら、今に蘇る歴史の物語を語り継ぐ。時にツッコミ、時に胸アツな筆さばきが自慢。歴史好きの皆さまに「そう来たか!」と言わせる快作に挑戦中。
べらぼう[用語解説]
■『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』
朋誠堂喜三二が書いた黄表紙(風刺本)。
鎌倉武士を「文に長けた者」「武に長けた者」「ぬらくら(怠け者)」に分ける物語で、
実は田沼派を皮肉る風刺作品。ところが読者には通じず、逆に定信の人気を高めてしまうという皮肉なヒット作。
■『画本虫撰(えほんむしえらみ)』
絵師・喜多川歌麿の代表作。
虫を題材に、狂歌(風刺詩)と絵を組み合わせた豪華絵本で、一見かわいらしく見えて実は社会風刺と人間模様が込められた芸術作品。
金持ちたちが「倹約令のおかげ」と誤解して買い求め、結果的に定信の改革を持ち上げる“皮肉の二乗”な名作。
■歌麿の妻・きよ(きよ)
耳が不自由な女性で、かつて歌麿の“黒く塗りつぶした絵”を拾ってくれた心優しい人物。
再会後、言葉の代わりに絵で想いを通わせる純愛の相手となる。
歌麿が「ちゃんとしてぇんだ」と誓う相手であり、彼の創作と人生の転機をもたらした“静かなミューズ”。
■鳥山石燕(とりやませきえん)
江戸時代の絵師・妖怪絵の名人。
『画図百鬼夜行』などの妖怪画で知られ、ドラマでは平賀源内と同じ羽織模様の男を見るという幻想的な場面で登場。
“絵に命を宿す男”として、創作の魂を象徴している。
■『鸚鵡言(おうむのことば)』
松平定信が書いた“武士の心得”の書。
「政(まつりごと)は凧を上げるようなもの」と説き、政治には“時・勢い・位”の三つの要が必要と説いたが、武士たちは「凧を上げれば国が治まる」と勘違い。
まじめな教訓がギャグになるという定信らしい“空回り改革”。
■『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』
恋川春町による風刺本で、『鸚鵡言』のパロディ。
定信の教えをそのまま“オウム返し”にしながら笑い飛ばすという、蔦重ら耕書堂一派の反骨精神の結晶。
黄表紙好きの定信が気づかず喜ぶという、江戸のユーモアと皮肉が光る名作。
![[べらぼう第34話あらすじ]<br>ありがた山の最後の別れ!松平定信の改革に蔦重ブチギレ!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/10/berabo-34-300x200.jpg)
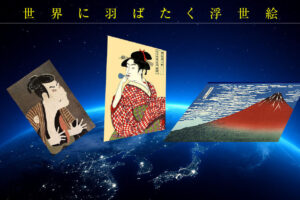
![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)
![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)