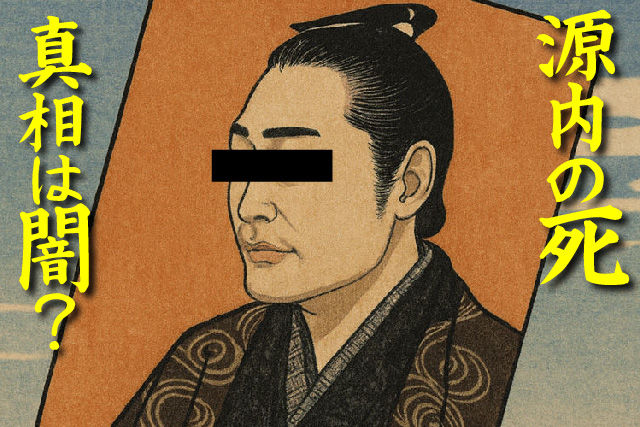
平賀源内の死因は、史料が少なく伝承も多いため、いまも結論が出ていません。
幕府記録は「病死」と記しますが、獄中の不衛生による感染症、事件時の負傷悪化、梅毒、アヘン影響など複数の可能性が並び立ち、真相は謎のままです。
では、なぜ源内の最期はここまで曖昧なのか? どの説がもっとも信ぴょう性を持つのか?
この記事では、当時の史料・伝承・最新研究をもとに、源内の「獄中死」の実像に迫ります。
平賀源内の死因を巡る3つの謎
江戸のマルチクリエイター・平賀源内は、発明家・戯作者・蘭学者として名を残しながら、その最期には多くの謎が残されています。ここでは、事件の背景から諸説までを整理し、源内の死をめぐるミステリーに迫ります。
【謎1】獄中死に至る事件の全貌
事件発生:殺傷に至る経緯
源内が獄に入るきっかけは、家禄に関する相談事から始まったと言われています。
もともとは些細な意見の食い違いでしたが、相手が源内を挑発したことで口論が激化し、ついには刃物を持ち出す事態へと発展しました。
源内は激情家として知られ、その場の感情に押されて相手を刺傷してしまいます。
当時の証言には「誤って刺した」「双方が激しく揉み合っていた」など複数の説が残され、事件の背景には社会的立場や人間関係の複雑なこじれがあったとも推測されています。
こうした混乱は、源内のその後の人生を大きく変えてしまいました。
逮捕と入牢:獄中生活の始まり
源内が収容されたとされる小伝馬町牢屋敷は、江戸の中でも最も過酷な施設として知られています。
狭く湿気のこもった牢内には、病人や負傷者が溢れ、衛生状態は劣悪でした。
囚人の多くは満足な食事も得られず、着衣も薄く、冬は寒気で震えるだけでなく、夏は害虫が蔓延する環境でした。
病気は日常的に発生し、特に破傷風や感染症で命を落とす囚人が多かったと記録されています。
源内のような文化人にとって、この過酷な環境は心身ともに大きな負担であり、健康悪化の一因となった可能性は高いと考えられます。
自首の真相と田沼意次との関係
事件後、源内は逃亡することなく自ら役所に出頭したとされています。
これについては、源内が当時の老中・田沼意次と親交を持っていたため、政治的な配慮が働くと信じていたからだとする説があります。
田沼政権は蘭学や新しい技術に理解があり、源内の活動を支援した側面もありました。
そのため源内は「正当に扱われる」と期待していた可能性があります。
しかし、田沼の影響力にも限りがあり、事件の重大性や世間の目がそのまま源内の処遇を左右したと考えられます。
この政治的背景は、源内の自首から獄中生活、その死に至る過程にも影を落としていたと言われています。
【謎2】公式記録に残る死因とその諸説
公式記録と史料が語る「病死」
幕府の死亡記録には源内の死因が「病死」とだけ記されています。
これは『御用留』に基づくとされ、死因の詳細や病名は伏せられています。
[参照元]国立国会図書館デジタルコレクション(御用留関連史料)https://dl.ndl.go.jp/
幕府の公式記録では、源内の死は「病死」と簡潔に記されています。
ただし病名は明らかにされず、どのような症状が見られたのか、どれほど急激に病状が悪化したのかといった詳細も不明です。
また、当時の役所による死亡記録は形式的で、政治的配慮や役所の都合によって簡略化されることも多く、記述の信頼性そのものが議論されています。
さらに、源内ほどの著名人であれば本来より詳しい記録が残っていてもおかしくないため、「あえて曖昧にされたのではないか」という憶測も生まれています。
破傷風説:事件時の傷口からの感染
破傷風説は、朋誠堂喜三二による『源内先生事蹟』にもしばしば関連して語られます。
同資料では源内が獄中で著しく衰弱していた様子が記録されており、負傷の悪化と不衛生な牢屋環境が死因に結びついた可能性が強調されています。
[参照元]早稲田大学 古典籍データベース『源内先生事蹟』で検索
逮捕前の喧嘩で負った傷が悪化し、破傷風を引き起こした可能性は多くの研究者が指摘しています。当時の牢屋敷は泥や汚物が溜まり、負傷者にとっては最も危険な環境でした。
破傷風菌は土壌から感染するため、牢内の湿った床や不衛生な寝具はまさに温床だったといえるでしょう。
また、江戸時代には破傷風の明確な治療法がなく、全身痙攣などが起きても原因を特定できなかったため、公式記録で「病死」と一括されてしまった可能性があります。
梅毒説:持病や私生活との関連
梅毒説は、大田南畝の随筆『翁草』に残る源内の奇行記録と関連づけられることがあります。
精神錯乱や衰弱がみられたという記述は、梅毒末期症状と重なる点が多く、研究者の間でしばしば引用されます。
[参照元]国立国会図書館デジタルコレクション『翁草』で検索
源内には梅毒を患っていたという言い伝えが残されており、奔放な私生活や交流の幅広さと結びつけられて語られてきました。
梅毒が進行すると精神錯乱や体力の著しい低下を引き起こすことがあり、晩年の源内が異様な言動を見せていたという記録とも符合します。
また、獄中では栄養状態が悪化するため、免疫力の低下によって病状が一気に悪化したとも考えられています。
梅毒説は破傷風説ほど確実ではないものの、複数の伝承が残されていることから、研究対象として今も注目されています。
アヘンとの関係:薬物使用の影響
源内は薬品研究に携わった際、アヘンを含む薬物にも触れていたとされています。
頼春水の『世説』には、源内の情緒不安定な振る舞いが描かれ、薬物影響説を裏づける一端として引用されることがあります。
[参照元]東京大学史料編纂所 デジタル史料『世説』で検索
薬草や薬物研究に深く携わっていた源内は、アヘンを含むさまざまな薬物にも触れていました。
研究目的であれ、慢性的に使用していた可能性は否定されず、これが体調悪化を招いたとする説もあります。
アヘンは依存性が強く、過度の使用は内臓に負担をかけ、判断力や精神状態にも影響を与えることがあります。
源内の奇行や情緒不安定な振る舞いが晩年に増えたという記録は、薬物影響説の根拠として扱われることがあります。
また、獄中で急に薬物を断たれたことによる禁断症状が死を早めた可能性も、一部の研究者が指摘しています。
【謎3】獄中死の伝承と史実の検証
事件に関する著名人の目撃証言
大田南畝や朋誠堂喜三二など、同時代を代表する文人たちは、源内の獄中での姿を記録として残しています。
南畝の『翁草』には、源内が次第に体力を失い、歩くことすら難しくなっていった様子が淡々と綴られています。
朋誠堂喜三二の『源内先生事蹟』には、源内が精神的にも追い詰められ、自責の念と孤独感に苛まれていた姿が描写されており、彼が置かれていた極限状態が生々しく伝わってきます。
彼らが残した記録は、獄中での源内がどれほど厳しい状況に置かれていたのかを知る、数少ない一次的証言として貴重です。
また、彼の異様な言動を「狂気」と表現する記述がある一方で、同情的な視線も感じられ、文人たちが源内という人物に抱いていた複雑な感情も読み取れます。
伝承が語る「非業の死」のイメージ
巷間では、源内の最期はしばしば「非業の死」として語り継がれてきました。
牢内で荒れ果て、病に侵されながら息絶えたという悲劇的なイメージは、講談や草双紙において脚色され、さらに強調されていきます。
フィクション作品では、獄中で狂乱しながら亡くなったり、理不尽な仕打ちの末に倒れたりするなど dramatized された描写が繰り返され、源内=奇才ゆえに悲劇的な最期を迎えた人物というイメージが広く定着しました。
こうした伝承は史実と距離があるものの、源内のキャラクター性や時代背景の影響によって生み出された文化的産物でもあり、後世に強い印象を残す一因となっています。
史料と伝承の乖離:真相の追求
史料には淡々とした短い記述が多く、獄中での様子や死因についても大きく踏み込んではいません。一方、伝承は劇的で感情的な表現を多く含み、物語性が強く付与されています。
この両者の乖離を比較して読み解くと、当時の人々が源内という人物にどのようなイメージを抱き、彼の死にどのような意味を重ねて語ってきたのかが見えてきます。
史料は事実の断片を伝えるのみですが、伝承は「天才は悲劇を招く」「異能の人は社会に理解されない」といった当時の価値観や社会心理を反映しています。
こうした差異を分析することは、単に真相に迫るだけでなく、江戸社会における人物評価や文化的背景を知る上でも重要な手がかりとなります。
平賀源内のミステリーを解き明かす
1. 研究者による考察と新たな仮説
死因特定の困難さと当時の医療水準
18世紀の医学では、死因を正確に特定することはきわめて難しく、症状の観察と経験則による推測に頼らざるを得ませんでした。
現代のような細菌学・血液検査・病理解剖が存在しなかったため、死因は「疝気」「中気」「病死」など抽象的な語でまとめられるのが常でした。
源内の場合も例外ではなく、獄中という特殊な環境での死亡であったにもかかわらず、担当の役人は詳細な記録を残さず、病名も記載されていませんでした。
また、牢屋敷の劣悪な環境では複数の病が併発していた可能性も高く、どれが致死的であったか判断することは現代の研究者にとっても極めて困難です。
さらに、当時は医療的知識が身分・地域によって大きく差があり、蘭学知識を持つ源内本人でさえ適切な治療を受けられなかったという点も、死因の特定を難しくする要因となっています。
近年の研究で注目される新たな学説
近年の歴史学・医学史の研究では、源内の精神状態や生活リズムの変化を手掛かりに、新しい学説が提示されています。
晩年の源内は躁鬱的な気質を示していたとする記録もあり、精神的ストレスと不摂生が持病を悪化させたとする見方があります。
また、蘭学者として化学実験を重ねていた源内は、有害な薬品に繰り返し触れていた可能性があり、長期的な中毒症状が死因に影響したという仮説もあります。
これに加え、牢屋敷での急激な生活環境の悪化――極度の寒冷、栄養不足、睡眠の欠如――が複合的に作用し、体全体のバランスが崩れた結果、急激な衰弱につながったとする総合説も提唱されています。
こうした新説は、単独の病気ではなく「複数の要因が重なり合った結果の死」である可能性を強調しており、源内の最期をより立体的に理解しようとする試みのひとつです。
2. 死の謎を解く鍵となる史料・文献
重要史料の紹介とその内容
『世説』や『源内先生事蹟』、『翁草』といった同時代の記録は、源内の最期を知るうえで欠かせない史料です。
これらには、獄中で源内が衰弱し、歩行や会話が困難になっていった様子、精神的に混乱していた可能性などが断片的ながら記されています。
また、多くの文献では源内が周囲から十分な看護を受けられなかった状況も示されており、牢屋敷での劣悪な環境が死を早めた可能性を裏づける材料にもなっています。
さらに、これらの史料は同時代の文人たちが書いたものが多く、源内との人間関係や感情が反映されている点も、読み解きの際に注意が必要です。
とはいえ、史料は後世の誇張や脚色が少なく、当時の空気感を伝える貴重な手がかりとなっています。
現代に残された情報の限界
現存する史料は部分的で、日付が欠落している箇所や、誰が何を見聞きしたのか明確でない記述も数多く含まれています。また、公式記録は事務的な処理を優先するため、死亡理由が深掘りされないまま簡潔に処理されることが多く、源内のような著名人でさえ例外ではありませんでした。そのため、後世の研究者は複数の史料を突き合わせて推測する方法を取らざるを得ず、決定的な答えを導き出すには情報が不足しています。さらに、牢屋敷の運営に関する詳細記録や医療行為に関する記述がほとんど残されていないため、「何が行われ、何が行われなかったのか」を特定することも難しい状況です。研究は続いていますが、決定的な答えを得るのは容易ではありません。
平賀源内に関する文化的影響
1. フィクションにおける平賀源内の描かれ方
大河ドラマなどの映像作品での源内像
ドラマでは「奇抜な天才」「破天荒な人物」として描かれることが多く、源内が持つ独創的な発想や突飛な行動が、映像作品の中で強調される傾向にあります。
特に大河ドラマなどでは、彼が西洋文明を積極的に学び、新しい文化を広めようと奔走する姿が情熱的に表現され、物語の中で強烈な個性として際立っています。
また、源内の死についても、史実以上にドラマチックに脚色されることがあり、獄中での苦悶や孤独が象徴的に描かれるケースも見られます。
こうした演出は、視聴者に源内の「異才ゆえの宿命」というイメージを強く印象づけてきました。
さらに、娯楽性を高めるため、源内の性格や行動に大胆なフィクションが加えられることも多く、歴史ファンの間では「史実との差異」について語られることもしばしばです。
蔦屋重三郎と時代背景:文化人としての側面
蔦屋重三郎との交流は、源内が当時の文化サークルの中心にいたことを物語る重要なエピソードです。
蔦重は出版界の革命児として知られ、多くの文人・絵師と関わりながら新しい文化を発信しましたが、その中に源内も深く関与していました。
二人の交流は、単なる仕事上のつながりではなく、互いに刺激し合う関係であったと伝えられています。
また、源内は狂歌会やサロンにも参加し、蘭学・出版・芸術の垣根を超えた文化人として幅広い活躍を見せました。
こうした多面的な活動は、映像作品や小説などで「時代の先駆者」としての源内像を描く際の大きな材料となっており、その人物像に深みを与えています。
文化人としての顔を持つ源内は、奇人としての側面と共存する形で描かれ、フィクション作品でも多彩な表情を見せています。
2. 平賀源内をモチーフにした作品と伝説
文学作品や漫画における「源内ミステリー」
源内の死因や事件を題材にしたフィクション作品は非常に多く、歴史小説・推理作品・漫画・ドラマなど、さまざまなジャンルで取り上げられています。
中でも、獄中死の謎を解き明かそうとするミステリー仕立ての作品は人気が高く、史実を踏まえつつも大胆な仮説や創作を交えて描かれることが多いです。
源内の奇行や変わった言動が、物語のキャラクターとして非常に扱いやすい点も、創作の題材として長く愛される理由に挙げられます。
また、近年では漫画やライトノベルで源内が主人公級の役割を担うこともあり、若い世代にも「謎に満ちた異才」として再評価されつつあります。
彼の死に関する未解明の部分や、周囲の人間関係の複雑さが、物語のテーマとして継続的に創作意欲を刺激し、今なお新しい作品が生まれ続けています。
まとめ:平賀源内の謎の死因は解明されたのか?
記事全体の要約と最終的な見解
これまでの史料・伝承・研究を総合すると、平賀源内の死因は依然として明確な答えを持ちません。
幕府記録の「病死」という一語はあまりにも簡潔で、獄中の極めて劣悪な衛生環境、事件時の負傷悪化による破傷風、私生活と関連づけられる梅毒、薬物研究に伴うアヘンの影響など、多数の可能性が同時に成立し得る状況にあります。
また、同時代の文人による一次記録と、後世に語られた伝承やフィクションの間には大きな隔たりがあり、その相互作用が源内の最期を一層“謎”として際立たせています。
つまり源内の死因は、史実の不足と伝承の豊かさが複雑に絡み合うことで、今もなお決定的な結論に至らないまま残された歴史的ミステリーなのです。
読者への問いかけと今後の展望
今後、新史料の発掘や医学史研究の進展によって、源内の最期に別の光が当たる可能性は十分にあります。
それでも、多くの可能性を内包した“解けない謎”であることこそが、源内という人物の魅力をいっそう高めているのかもしれません。
あなたは、数ある説のうちどれが最も真実に近いと感じるでしょうか?
![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)
![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)
![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)


![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)