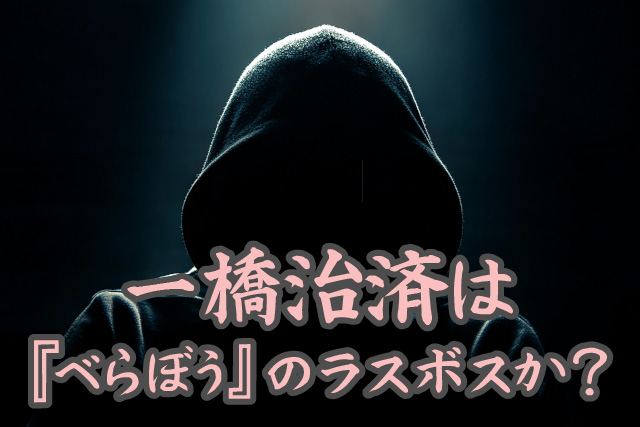
一橋治済(ひとつばし はるさだ)は、江戸時代のなかごろから終わりごろにかけて活躍した人物です。
将軍の血をひく名門・一橋家のリーダーであり、自分の息子を将軍にするなど、大きな力をもっていました。
2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』でも話題になり、「黒幕ではないか」とささやかれるほどの人物。一見やさしそうですが、実はとても頭が切れて、自分の立場を守るためにはどんな手も使ったといわれています。
この記事では、そんな一橋治済の人生や政治でのかかわりを、やさしく解説していきます。
Contents
一橋治済ってどんな人?
一橋治済は、8代将軍・徳川吉宗(よしむね)の孫であり、11代将軍・徳川家斉(いえなり)の本当のお父さんでもあります。つまり、とてもすごい家に生まれた人なんですね。
治済が生きたのは1751年(宝暦元年)から1827年(文政10年)まで。江戸時代のなかでも、幕府の力がゆれていた「改革の時代」にあたります。政治の中では、自分の家や地位を守るために、いろいろな作戦を使ったことで知られています。
治済の子ども時代と家のこと
治済は、1751年に一橋家の当主・徳川宗尹(むねただ)の四男として生まれました。はじめの名前は「松平豊之助(とよのすけ)」といいます。
14歳のときにお父さんが亡くなり、一橋家のリーダーになります。「徳川民部卿治済(とくがわ みんぶきょう はるさだ)」と名乗りはじめ、しだいに幕府の政治に関わるようになりました。
息子・家斉が将軍になるまで
治済の息子・家斉は、1781年に10代将軍・徳川家治(いえはる)の養子になります。じつは家治は、田安家(たやすけ)の定信(さだのぶ)という人を後つぎにしたいと思っていたのですが、当時の権力者・田沼意次(たぬま おきつぐ)が別の家に定信をうつし、家斉を選んだのです。
そして1786年に家治が亡くなり、次の年には15歳の若さで家斉が11代将軍になります。まだ子どもだったので、治済が裏でいろいろと助けていたといわれています。
田沼意次を追い出し、松平定信を登用するまで
~「息子を将軍にする」ための、治済の見えない戦い~
一橋治済(はるさだ)は、自分の長男・家斉(いえなり)を将軍にするために、幕府の内部でさまざまな動きをしていました。そのなかで、特に大きな転機となったのが、10代将軍・徳川家治(いえはる)の死です。
家治の死と、田沼への不信感
天明6年(1786年)、将軍・家治が病気で亡くなります。このとき、家治は「水腫(すいしゅ)」という病気で体がむくみ、つらい状態でした。
治療にあたったのは、老中・田沼意次(たぬま おきつぐ)が連れてきた町医者。ところが、その医者が調合した薬を飲んだあと、家治は急に亡くなってしまいます。
このことがきっかけで、「あの薬に何かあったのでは?」「田沼が将軍を殺したのではないか?」という、うわさが広まりました。はっきりした証拠はありませんが、不信感が高まりました。
田沼失脚と、治済の暗躍
この「うわさ」や混乱を利用したのが、一橋治済です。家治が亡くなったことで、治済の息子・家斉が将軍に就任する流れが生まれます。ですが、まだ若くて政治の経験がない家斉には、後見役(アドバイザー)が必要でした。
ここで治済は、田沼を政治の中心から追い出し、自分のいとこでもある松平定信(まつだいら さだのぶ)を後見役にすえることに成功します。
定信は名君・吉宗の孫であり、治済とも血のつながった親せきです。これで治済は、自分の息子を将軍にし、そのすぐそばに信頼できる人物を置くことに成功したのです。
尊号事件と、松平定信との対立
~「大御所になりたい治済」と、「絶対に許さない定信」~
その後、家斉の時代になると、政治の表舞台では松平定信が活躍していましたが、裏では治済が大きな影響力をもち続けていました。ところが、2人のあいだにはやがて深い対立が生まれます。
尊号事件とは?
寛政元年(1789年)、京都の天皇・光格天皇(こうかくてんのう)が、自分の父・閑院宮典仁(かんいんのみや すけひと)に、「太上天皇(たいじょうてんのう)」という尊号を贈りたい、と申し出ました。
「太上天皇」というのは、ふつうは元・天皇に対して贈る、とても名誉ある称号です。ところが、定信はこれに強く反対します。
なぜなら、「天皇の父に太上天皇を贈る」という前例をつくってしまうと、政治の力関係が変わってしまう可能性があったからです。江戸幕府としては、朝廷(天皇のいる京都)が政治に強く関与してくることをとても警戒していたのです。
裏にあった、もうひとつの思惑
でも実は、この「尊号事件」には、もう一つの裏の理由がありました。
それは、一橋治済が「自分も“太上将軍”や“大御所”として正式に西の丸(にしのまる)に入ろうとしていた」という話です。つまり、将軍の父として、自分も特別な地位を得ようとしていたのです。
松平定信は、この「治済の大御所入り」を強く警戒していたとされています。「朝廷が父に尊号を贈るのなら、幕府でも治済が同じような立場を得てしまう。そうなれば、治済が幕府を牛耳ってしまうかもしれない」——そんな危機感があったのです。
こうして、尊号をめぐる表の争いと、「治済 vs 定信」という裏の権力争いが重なっていきました。
対立の決着と、定信の退場
治済と定信の関係はどんどん悪化し、ついに寛政5年(1793年)、定信は老中(政治のトップ)と将軍補佐の役職を辞めてしまいます。
このとき、定信は「政治からの引退」としてはめずらしく、自分から江戸を離れ、白河(しらかわ/福島県)に引きこもるように去っていきました。
結果として、治済は自分の息子・家斉を将軍にしたうえで、そのそばにいた“ライバル”である定信を政治の場から遠ざけることにも成功したのです。
晩年とその後
治済は1791年に、息子の徳川斉敦(なりあつ)に家のあとをゆずって隠居しました。しかし、将軍の父という立場から、政治への影響力は最後まで残っていました。
晩年には、朝廷から「従一位」や「准大臣」といったとても高い地位をもらい、ゆたかな生活をおくります。贈り物もたくさん受け取り、向島には立派な別荘もかまえたそうです。
1827年、77歳で亡くなり、上野の東叡山(とうえいざん)におくられました。亡くなったあとには、なんと「太政大臣」の位ももらっています。
ドラマで描かれる治済のすがた
1.『べらぼう』の治済:やさしい仮面をかぶった冷酷な父
2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、俳優・生田斗真さんが一橋治済を演じています。
このドラマでは、治済は表向きには優雅で教養のある公家のような人物として描かれています。たとえば、文や詩、和歌に親しみ、家族を大切にするような穏やかな振る舞いを見せます。でも、その優しさの裏には「冷静で計算高い権力者」というもう一つの顔があるのです。
特に注目されているのは、「わが子・家斉を将軍にするためなら、どんな策略も使う」という点です。敵対する田沼意次や松平定信の動きを冷静に見極め、時に味方するように見せながら、最後には自分にとって有利なように事を運ぶ。まるで将棋の名人のように、先を読んで手を打っていく姿がスリリングに描かれています。
こんなシーンがあるかも?
・表ではにこやかに酒を酌み交わしながら、裏では密かにライバルの失脚を計画
・自分は手を汚さず、部下や家臣を使って障害を取り除く
・息子・家斉に「将軍になるための心得」をささやき、陰から支える
こうした描写によって、治済は「黒幕」のような存在として登場します。視聴者は「この人、何を考えてるんだろう?」とドキドキしながら物語を見守ることになります。
『大奥 Season2』の治済:女性として描かれた治済の強さと恐ろしさ
2023年放送のNHKドラマ『大奥 Season2』では、原作がよしながふみさんの漫画で、男女の立場が逆転した江戸時代が舞台になっています。この作品の中で、一橋治済は“女性”として登場し、女優・仲間由紀恵さんが演じました。
このバージョンの治済は、見た目は上品で優雅な女性ですが、その心の奥はとても冷酷。自分の家(=一橋家)の権力を守るためには、笑顔の裏でどんな残酷な手も使います。
たとえば…
- 自分の子を将軍にするため、他の有力者の弱みを握って失脚させる
- 「家を守るのは母の務め」と言いながら、敵に情けをかけず冷たく切り捨てる
- 政治の裏側を知り尽くし、若い将軍をあやつるように導いていく
こうした姿は「女大奥のボス」として、とても迫力があります。現代の感覚で言えば、「社長の母親で、実は会社を裏で動かしている会長」のような存在かもしれません。
なぜ治済はこう描かれるのか?
史実では、一橋治済がどれだけ直接手を下したかははっきりしていません。しかし、実際に息子・家斉を将軍に押し上げ、田沼意次を退け、松平定信を登用・排除するなど、江戸幕府の中枢に大きな影響を与えたことは事実です。
そのため、ドラマでは「表の顔と裏の顔を持つ謀略家」として描かれることが多いのです。これは「治済がどれだけ人を動かし、幕府の中で存在感を発揮したか」をドラマ的にわかりやすく表現する方法なのです。
ドラマに登場する一橋治済は、いつも「やさしさ」と「冷酷さ」をあわせ持つ、二面性のある人物として描かれます。そして、その二面性があるからこそ、物語に深みや緊張感が生まれます。
史実に基づきつつも、脚色されたドラマの治済像を通じて、「政治の裏で動く人物の恐ろしさ」「人の心をつかんで動かす技術」などを感じ取ることができるのではないでしょうか。
一橋治済とは?[まとめ]
一橋治済は、江戸幕府の政治に深く関わった重要な人物です。将軍の実の父として、表からも裏からも力をふるいました。田沼意次を追い出し、松平定信を登用するなど、政治の流れを変えるような行動を数多くとっています。
ぜいたくな生活を楽しむ一方で、頭をつかってさまざまな作戦をめぐらせた治済のすがたは、まさに「幕府の黒幕」ともいえる存在です。
江戸時代のウラ側を知るうえで、彼の生き方を知っておくことはとても大切です。
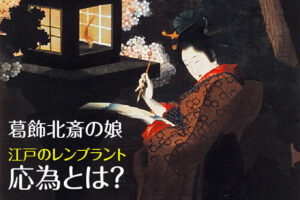
![[べらぼう第28話あらすじ]<br>意次、覚醒。父の魂が治済に突き刺さる江戸城バトル回、震えた!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/08/berabo-28-300x200.jpg)
![[べらぼう第48話あらすじ]<br>蔦重死すとも生きている!涙と笑いの江戸エンタメ終幕](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-48-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>蔦重の神采配!毒饅頭リターンで幕府の闇に切り込む!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-47-300x200.jpg)
![[べらぼう第46話あらすじ]<br>写楽誕生の裏で動き出す不気味すぎる治済の影](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/12/berabo-46-300x200.jpg)
![[べらぼう第45話あらすじ]<br>蔦重が仕掛けた“写楽集団説”!歌麿との運命のタッグ復活か!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-45-300x200.jpg)

![[べらぼう第44話あらすじ]<br>源内、生きてるってマジ!? 七ツ星の龍と“死を呼ぶ手袋”の謎が再始動](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-44-300x200.jpg)

![[べらぼう第43話あらすじ]<br>歌麿と蔦重、二十年の絆が散る夜——そして定信の絶叫が響く!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-43-300x200.jpg)

![[べらぼう第42話あらすじ]<br>定信の御触れに泣き面に蜂!蔦重×歌麿、決別の夜!](https://5orb.net/wp/wp-content/uploads/2025/11/berabo-42-300x200.jpg)